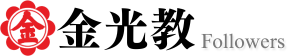お知らせ
令和6年度輔教志願者講習会のご案内
令和6年度の輔教志願者講習会を開催します。
輔教制度は、教祖時代の自由な布教精神を頂き直し、信徒が積極的に本教の信心を伝え現す布教活動に参画することを願って、平成4年に発足しました。
輔教は、「本教の信心を伝えるため、進んで教会活動を担うとともに、教団活動に参画する」と意義づけられており、435教会1196人(令和6年3月25日付)の輔教の方が、それぞれの持ち場立場にあって、神を現す信心実践を進め、御神願成就に向けて活動しています。
輔教は、在籍教会長の推薦を受けて、輔教志願者講習会を受講することにより、教主金光様からご任命を頂きます。任期は4年間で、本部や各教区で開かれる輔教研修会を受講すれば、再任を願い出ることができます。
輔教になるために受講が義務づけられているこの講習会は、年に1回本部で開催され、全国から「輔教として御用をさせていただきたい」という志を持った信奉者が集います。
講義では、金光教の教義や教団体制をはじめ、輔教の意義や求められる働きについて学び、「迎えられる立場から迎える立場へ」という意識が醸成され、人を助ける視点に立って、これまで培った信心を見直すことができます。また、年代別の班別懇談や、ご霊地宿泊施設での交流をとおして、全国のお道の仲間と出会い、信心に生きる喜びを再確認することができます。
今日の時代社会に、教会がご神願成就の拠点として、生神金光大神取次の働きをいっそう展開するには、教師と共にご神願を担う輔教(信徒)の働きがますます重要になってきます。多くの方がこの講習会を受講して、輔教にお取り立ていただかれますことを願っています。
開催要項
日時
8月24日(土)13時~8月25日(日)12時50分
会場
金光教本部
受講料
無料
講義内容
講義①「金光教について」
講義②「教団の仕組みと働きについて」
講義③「輔教の役割について」
輔教の実践発表
出願要項
以下の要領で必要書類を調え、在籍教会が所在する教区のセンターへ提出してください。
後日、受講許可通知と受講についての詳細を在籍教会長を通じて本人に通知します。
出願資格
令和6年12月1日時点で、18歳以上の信徒。ただし、教規第169条第2項の規定に該当する方は出願できません。
出願手続き
- 必要書類 受講願(所願届様式第62号)3部
受講願はコピーでも構いません。ただし、押印は全て朱肉を使用し、2部を在籍教会が所在する教区のセンターに提出、1部は教会控えにしてください。
目、耳、足などが不自由で、受講に支障や不安があると思われる場合は、受講願(健康状態欄)にその旨を記入してください。会場の配慮をいたします。
なお、受講願(所願届様式第62号)は、金光教ホームページの所願届様式ページからダウンロードできます。 - 出願締め切り 7月5日(金)【消印有効、締め切り厳守】
注意事項
- 輔教になるためには、この講習会の全講義を修了しなければなりません。必ず全日程を受講してください。遅刻や早退は原則として認めません。
-
講習会受講期間の宿泊、食事などは、各自で手配してください。その際、金光北ウイング(光風館)、土佐家には、輔教志願者講習会時の宿泊料が適用されますので、申し込みの際に、輔教志願者講習会受講者であることを申し出てください。
金光北ウイング(光風館) 電話0865-42-7008
宿泊3300円(税込)
利用日の3カ月前から予約可能
売店の営業や食事の提供はありません。
土佐家 電話0865-42-2157
宿泊5000円、夕食1200円、朝食800円(いずれも税込)
※相部屋での料金となりますので、個室希望の方は要相談。
桂家 電話0865-42-3161
1人部屋5500円、2人部屋5000円/人、3人部屋4500円/人、4人部屋4000円/人(いずれも朝食込の税込価格)、夕食は要相談。
※各施設とも宿泊料に浴衣などは含まれていませんので、必要な方は持参されるか、宿舎備え付けの貸し出し用(別途料金)をご利用ください。福山や倉敷などには、ビジネスホテルもあります。
日程
<第1日>
12 : 00 受付
13 : 00 開会行事
14 : 00 講義①(90 分)
15 : 40 講義②(50 分)
17 : 00 班別懇談(60 分)
18 : 00 終了
<第2日>
3 : 45 教主金光様お出ましお迎え※
4 : 00 本部広前ご祈念※
5 : 15 朝の教話※ ※は自由参加
8 : 00 講義③(90分)
9 : 45 輔教の実践発表(30分)
10 : 30 質疑応答
12 : 15 閉会行事
12 : 50 解散
令和6年度 輔教研修会のご案内
輔教再任時の義務である輔教研修会は、各教区で開催していた輔教集会と連動して行うことになり、全教区で受けられるようになりました。
任期満了輔教で再任を願う方は、どこの教区でも構いませんので、輔教集会に参加し、その前後どちらかに行われる輔教研修会(約1時間)を受講した上で、再任の手続きを行ってください。
なお、信心を培い、輔教の役割を確認するために、輔教集会には必ず参加した上で、研修会を受講することとします。研修会のみの受講は認められません。
本年度の開催日時、会場は次のとおりです。(新型コロナウイルス感染症の拡大状況により変更の可能性あり)
任期満了輔教には、開催の案内と受講願を送付していますので、どこの会場で受講するか決定した後に、それぞれの締め切りまでに、受講願を提出するようにしてください。
既に受講願を提出された方について、延期後の日程で、受講希望会場に変更がなければ、連絡は必要ありません。
会場を変更される、または受講をやめる場合のみ、本部教庁布教部または在籍教区のセンターに連絡してください。
いずれの場合も受講願の再提出の必要はありません。
令和6年度輔教研修会の会場日程一覧
| 会場 | 日程 | 開催場所 | 提出締め切り |
| 北海道 | 7月7日(日) | 金光教北海道教務センター | 5月20日 |
| 東北 | 9月8日(日) | 仙台市内 | 7月10日 |
| 関東 | 6月23日(日) | 金光教館イーストホール | 5月5日 |
| 信越 | 7月13日(土) | 上越市内 | 5月25日 |
| 東海 | 6月23日(日) | 名古屋港湾会館 | 5月5日 |
| 東近畿 | 7月7日(日) | 京都市生涯学習総合センター | 5月20日 |
| 中近畿 | 6月15日(土) | 玉水記念館 | 4月30日 |
| 西近畿 | 9月7日(土) | 金光教西近畿教務センター | 7月10日 |
| 東中国 | 9月8日(日) | 金光北ウイング やつなみホール |
7月10日 |
| 西中国 | 9月16日(祝) | 安芸区民文化センター | 7月10日 |
| 四国 | 6月16日(日) | 新居浜市内 | 4月30日 |
| 北九州 | 6月16日(日) | 金光教北九州教務センター | 4月30日 |
| 南九州 熊本会場 |
8月25日(日) | 金光教二本木教会 | 7月10日 |
| 南九州 大分会場 |
9月8日(日) | 金光教大分教会 | 7月10日 |
| 金光① | 8月31日(土)13時~ 9月1日(日)13時 |
本部教庁会議室 | 7月10日 |
| 金光② | 9月5日(木) | 本部教庁会議室 | 7月10日 |
手続き
① 「輔教研修会受講願」に必要事項を記入の上、2部コピーし、全てに押印する。
その際、受講したい教区名または会場名と日付を忘れないように記入すること。
② 1部は本人控えとし、2部を在籍教会が存在する教区の布教センターまたは教務センターに送付する。
③ 後日、本部からは受講願を受理した旨の通知を送付し、その後、当該センターから輔教集会の案内が届くので、それに従って出席する。
④ 当日までに変更が生じた場合は本部に連絡し、代わりに受講する会場を知らせる。その際、あらためて受講願を出す必要はない。
※受講出来ない事情があり、継続を願う場合は「輔教再任手続き延期願」を提出する。
「輔教研修会受講願」及び「輔教再任手続き延期願」はこちらからダウンロード可能です。
【連絡先】
金光教本部教庁布教部 輔教担当
平日9時~17時:0865-42-6453 / 時間外:0865-42-3111 / E-mail:ikusei@konkokyo.or.jp
令和6年度輔教集会のご案内
関東
日時
6月23日(日)13時30分~15時00分
会場
金光教館イーストホール(東京都千代田区神田和泉町1番地)及び、オンライン(Zoom)
内容
・講話「願いを受けて 願いを持つ」 講師:中谷智美氏(三重・五十鈴川/輔教)
・質疑応答
経費
参加費無料。交通費・通信費は自己負担。
申込み
FAX、またはE-mailにて、6月7日までにお申込み下さい。
FAX 03-3818-6323
E-mail:tokyo@konkokyo.or.jp
※「オンライン参加」を希望される方は、ZoomミーティングID及びパスコードをお知らせする必要から、E-mail宛にお申し込みください。
備考
受講に関するお問い合せや、申込後に受講できなくなった場合、東京センター(TEL:03-3818-6321 E-mail:tokyo@konkokyo.or.jp)までご連絡ください。また、季節柄、会場では冷房が入ります。
東海
日時
6月23日(日)13時15分~16時30分
会場
名古屋港湾会館 第1会議室 (名古屋市港区港町1―11)
テーマ
「知ってみよう!あなたの知らない金光教」
内容
講話、グループワーク(班別)、全体会
・講話 講師 八木知広師(京都・綾部)
講題 「金光様に導かれ、神のおかげに目覚め」
・グループワーク 教内用語を使わずに信心について伝える体験にトライ
注意事項
開催通知同封のグループワークのための事前記入シートを記入のうえ、当日持参してください。
会場側の指示により、当日、会場内では可能な限りマスクをご着用ください。
備考
この度は、輔教集会と輔教研修会を併せて一つの会合として開催いたします。また、オンラインでの出席は受け付けておりませんので、ご了承ください。
信越
日時
7月13日(土)13時30分~16時30分
会場
金光教信越教務センター及び救急市民交流プラザ(富山県射水市)※オンライン参加も可能です
内容
講話、懇談
講師
石塚陽子師(新潟・佐渡)
申込締切
6月25日(火)
申込先
金光教信越教務センター
〒942―0001 新潟県上越市中央3丁目4―27
TEL・FAX 025-5440-0564 E-mail konko_shin@yahoo.co.jp
備考
輔教研修会は、輔教集会後に開催されます。